・2006.04.10
・2006.04.10(2)
・2006.04.14
・2006.04.14(2)
・2006.04.27
・2006.04.28
・2006.05.22
・2006.05.22(2)
・2006.05.29
・2006.06.01
・2006.06.01(2)
・2006.06.02
・2006.06.05
・2006.06.06
・2006.06.08
・2006.06.16
・2006.06.19
・2006.06.23
・2006.07.11
・2006.07.16
・2006.07.26
・2006.08.01
・2006.08.03
・2006.08.04
・2006.08.09
・2006.08.14
・2006.08.22
・2006.08.23
・2006.08.23(2)
・2006.08.28
・2006.08.30
・2006.09.05
・2006.09.08
・2006.10.04
・2006.10.06
・2006.10.10
・2006.10.11
・2006.10.20
・2006.10.26
・2006.10.27
・2006.10.30
・2006.10.31
・2006.11.07
・2006.11.09
・2006.11.09(2)
・2006.11.09(3)
・2006.11.09(4)
・2006.11.10
・2006.11.16
・2006.11.17
・2006.11.20
・2006.11.20(2)
・2006.11.22
・2006.12.01
・2006.12.02
・2006.12.05
・2006.12.13
・2006.12.14
・2006.12.15
・2007.01.11
・2007.01.15
・2007.01.22
・2007.01.22(2)
・2007.01.26-27
・2007.02.05
・2007.02.13
・2007.02.16
・2007.02.16(2)
・2007.02.20
・2007.02.22
・2007.03.01
・2007.03.06
・2007.03.09
・2007.03.10
・2007.03.13
平成18年度の行事は全て終了いたしました。
このページのTOPへ
■21COE講演会(No.1)が行われました。
日時:平成18年4月10日(月)15:00~ 【報告書】
講師:Prof. John E. Hearst (University of California, Berkeley)
演題:"My life with DNA and Psoralens"
場所:理学研究科2号館130号室
世話人:京都大学理学研究科 化学専攻 杉山 弘 TEL:内線4002
案内:
ソラレンは光照射下でDNAと共有結合を形成することが知られ光治療や分子生物学的な手法として用いられています。ハースト教授はソラレンのDNAとの光反応について分子レベルで明らかにしたこの分野での第一人者であり、さらにその応用についても検討を精力的にされ、昨年にはNature Reviewにも総説を執筆されています。
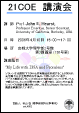 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.2)が行われました。
日時:平成18年4月10日(月)17:00~ 【報告書】
講師:Prof. Matthias Roegner (Ruhr-universitaet Bochum, Germany)
演題:Proteomics of Membrane Proteins and Dynamics of Photosystem 2: Useful Interrelation
場所:理学研究科2号館129号室
世話人:京都大学理学研究科 化学専攻 三木 邦夫 TEL:内線4029
京都大学大学院地球環境学堂 地球親和技術学廊 三室 守 TEL:内線6855
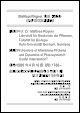 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.3)が行われました。
日時:平成18年4月14日(金)16:30~ 【報告書】
講師:Prof. John Michael Brown (Oxford University, UK)
演題:Mechanism-based Adventures in Homogeneous Palladium Catalysis
場所:理学研究科2号館130号室
世話人:京都大学理学研究科 化学専攻 林 民生 TEL:内線3983
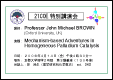 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.5)が行われました。
日時:平成18年4月14日(金)16:00~ 【報告書】
講師:Prof. Wolf-D. Woggon (バーゼル大学、スイス)
演題:Lessons from Enzymes and Enzyme Models
場所:桂キャンパスA2棟302号室
世話人:京都大学工学研究科 合成・生物化学専攻 浜地 格 TEL:内線2754
案内:Woggon教授は、ヘム酵素P−450の生化学および合成ポルフィリンを用いたモデル系の構築において優れた業績を挙げておられる生物有機化学者です。御来聴を歓迎致します。
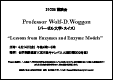 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.4)が行われました。
日時:平成18年4月27日(木)10:00~ 【報告書】
講師:Prof. Johann Deisenhofer 1988年ノーベル化学賞受賞
(University of Texas Southwestern Medical Center, USA)
演題:Structural Insights into Cholesterol Homeostasis
場所:京都大学百周年時計台記念館2階 国際交流ホールⅡ
世話人:京都大学理学研究科 化学専攻 三木 邦夫 TEL:内線4029
案内:
J. Deisenhofer博士は,光合成反応中心複合体のX線結晶解析の成功によって,1988年のノーベル化学賞を受賞したタンパク質結晶学者です.今回は,コレステロールホメオスタシス(恒常性)に関与するタンパク質の構造生物学研究についてお話しいただきます.
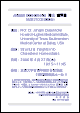 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.6)が行われました。
日時:平成18年4月28日(金)15:00~ 【報告書】
講師:周 大新 教授 (Prof. Tashin J. Chow)
(中央研究院化学研究所、台湾)
演題:Organic Electroluminescence Materials and Devices
場所:桂キャンパスA2棟308号室
世話人:京都大学工学研究科 合成・生物化学専攻 吉田 潤一 TEL:内線2726
案内:
His interests are in the areas of physical organic chemistry and photochemistry. Current works are focused onto (1) organic luminescent dyes as emitting materials for LED (2) rigid rod-shaped molecules and (3) polycyclic hydrocarbons. Ref.: Chem. Mater. 2006, 18, 832.
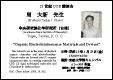 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.9)が行われました。
日時:平成18年5月22日(月)15:00~17:00 【報告書】
講師:Prof. Devens Gust (アリゾナ州立大学)
演題:"Photochromic Molecular Switches and Logic Gates."
場所:理学研究科6号館571室
世話人:京都大学理学研究科 化学専攻 大須賀 篤弘 TEL:内線4008
案内:
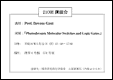 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.10)が行われました。
日時:平成18年5月22日(月)17:00~19:00 【報告書】
講師:Prof. Tomas Torres (アウトノマ大学)
演題:Designing and Synthesizing Phthalocyanines and Related Compounds for Optoelectronic applications
場所:理学研究科6号館571室
世話人:京都大学理学研究科 化学専攻 大須賀 篤弘 TEL:内線4008
案内:
 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.14)が行われました。
日時:平成18年5月29日(月)14:00~15:30 【報告書】
講師:Prof. Josef Michl (University of Colorado at Boulder)
演題:Advances in the Organic Chemistry of Carborane Anions and Radicals
場所:化学研究所 中会議室(C473)
世話人:京都大学化学研究所 村田 靖次郎 TEL:0774-38-3177
 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.7)が行われました。
日時:平成18年6月1日(木)16:30~ 【報告書】
講師:Prof. Jean Le Bideau (Université Montpellier2, France)
演題:Materials synthesis in ionic liquids:
new routes for new monolithic electrolytes and chromatographic columns
場所:理学研究科6号館203室
世話人:京都大学理学研究科 化学専攻 中西 和樹 TEL:内線2925
案内:
Jean Le Bideau博士は、イオン性液体を溶媒とした無機系および有機無機複合系固体材料の液相合成プロセスを開発すると共に、合成された材料の固体電解質としての特性評価や、多孔性液相分離媒体としての応用を開拓している。ナノスケールからマクロスケールにわたる特徴的な網目構造と分子間相互作用を利用して、イオン性液体を保持した固体材料、あるいはイオン性液体を一時的な鋳型とした多孔性固体の構造制御を行い、散乱法や核磁気共鳴法を駆使して、反応の微視的な特徴を明らかにしている。有機、無機合成に携わる研究者はもとより、電気化学、分析化学関連の研究者の来聴を歓迎します。
 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.11)が行われました。
日時:平成18年6月1日(木)15:00~ 【報告書】
講師:Prof. H. Yang (University of California at Berkeley, US)
演題:High-resolution single-molecule spectroscopy and 3D single-particle tracking
場所:理学研究科6号館571室
世話人:京都大学理学研究科 化学専攻 寺嶋 正秀 TEL:075-753-4026(FAX:4000)
要旨:The recent advances in time-dependent studies of single molecules or particles is discussed. Using ideas from information theory and statistical sampling, it is now possible to quantitatively measure the conformational distribution, the potential of mean force, and the velocity-distance distribution (phase-space density) from a single molecule. These new methods are used to study protein folding, as well as the dynamics in conformational fluctuation and enzymatic reaction. We also discuss our latest experimental and theoretical progresses in doing optical single-molecule measurements on a single-particle that freely moves in 3D, and sum-frequency generation chiral imaging microscopy.
生体分子の1分子観測で新進気鋭の活発な研究者です。多くのご来聴をお願い申し上げます。
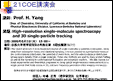 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.12)が行われました。
日時:平成18年6月2日(金)15:00~16:00 【報告書】
講師:Prof. King-Fu Lin (National Taiwan University)
演題:Fabrication of the organic/inorganic hybrid nanostructures via self assembly of
amphiphilic light emitting molecules
場所:化学研究所 新4階セミナー室(C469)
連絡先:京都大学化学研究所 磯田 正二 TEL:0774-38-3051
案内:この度、国立台湾大学・物質科学科のK.-F. Lin教授の化学研究所での講演会を上記のとおりの要領で開催いたします。Lin教授の最近の研究対象は有機無機複合材料の開発と機能性発現で、当該分野の第一線で活躍されています。皆様にはお忙しいことと存じますが、是非お誘いの上多数のご来聴をお願いいたします。
 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.13)が行われました。
日時:平成18年6月5日(月)13:30~ 【報告書】
講師:Prof. G. Petrakovskii (Institute of Physics SB RAS)
演題:Magnetism of Two-Dimensional Spin Systems
場所:京都大学基礎物理学研究所(新棟)K202号室
連絡先:京都大学理学研究科 化学専攻 陰山 洋 TEL:075-753-3991
案内: 下のポスターをご覧下さい。
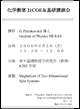 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.15)が行われました。
日時:平成18年6月6日(火)16:00~ 【報告書】
講師:Dr.Jörg Ackermann (France)
演題:Hybrid bulk heterojunction solar cells: a novel approach for flexible photovoltaics
場所:京都大学桂キャンパス A2棟118号
連絡先:京都大学工学研究科 分子工学専攻 今堀 博 TEL:075-383-2566
案内: 下のポスターをご覧下さい。
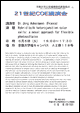 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.8)が行われました。
日時:平成18年6月8日(木)16:00~ 【報告書】
講師:福島 孝典 先生
(科学技術振興機構 ERATO-SORST ナノ空間プロジェクトグループリーダー)
演題:Low-Dimensional Soft Nanomaterials Based on Graphitic Nanostructures
グラファイト構造を有する低次元ソフトナノマテリアルの創成
場所:理学研究科6号館571室
世話人:京都大学理学研究科 化学専攻 大須賀 篤弘 TEL:内線4008
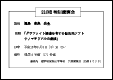 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.16)が行われました。
日時:平成18年6月16日(金)14:00~(6/11訂正)【報告書】
講師:Prof. Michael L. Klein (University of Pennsylvania, US)
演題:"Nothing Amuses More Harmlessly Than Computation..."
場所:化学研究所新4階(西)セミナー室(C-469号室)
世話人:京都大学化学研究所 中原 勝 TEL:内線3070
案内:
Klean博士は、膜・界面現象に対する計算化学の大家です。今回の講演では、疎視化モデルを用いた、ナノからメゾスケールの自己組織化系の構造形成とダイナミクスに関する最新の知見をご講演いただきます。多数の皆様のご来聴を歓迎いたします。
 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.17)
化学教育トリニティH18年度第1回特別講演会 が行われました。 【報告書】
(京都大学工学研究科「化学教育トリニティ」プログラム主催、斉藤COE、小久見COE共催)
日時:平成18年6月19日(月)15:30~
講師: Prof.Paul Anthony Madden (エジンバラ大学,UK)
演題:From first-principles to material properties:
realistic studies of ionic melts and their electrochemical interface.
場所:京都大学 桂キャンパス 化学系講義室4(A2棟307号室)
世話人:京都大学工学研究科 分子工学専攻 佐藤 啓文 TEL:075-383-2548
案内:
Paul A. Madden 教授は、分子動力学(MD)法を中心とした計算機シミュレーションによる物質の構造と性質の研究において世界的指導者のお一人です。現在は、新しいシミュレーション用ポテンシャル関数の開発やCPMD などの基礎研究、およびこれらを基にした材料開発等を行っておられます。今回、日本学術振興会の外国人招聘研究者(短期)として滞在されており、この講演はその一環として行われるものです。
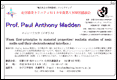 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.18)が行われました。
日時:平成18年6月23日(金)16:00~17:30 【報告書】
講師:Prof. Fernando Langa (Castilla-La Mancha University (UCLM), Spain)
演題:From Fullerenes to Carbon Nanotubes: The Route for Functionalization
場所:京都大学桂キャンパス A2棟308号室
世話人:京都大学工学研究科 分子工学専攻 今堀 博 TEL:075-383-2566
案内:Fernando Langa教授はフラーレン化学で著名な有機化学者です。ご来聴を歓迎します。
【参考文献】
1. Delgado, J. L.; de la Cruz, P.; Langa, F.; Urbina, A.; Casado, J.; Lopez Navarrete, J. T. Chem. Commun. 2004, 1734-1735.
2. Alvaro, M.; Atienzar, P.; de la Cruz, P.; Delgado, J.L.; Garcia, H.; Langa, F. J. Phys. Chem. B. 2004, 108, 12691-12697.
3. Alvaro, M.; Atienzar, P.; de la Cruz, P.; Delgado, J.L.; Troiani, V.; Garcia, H.; Langa, F.; Palkar, A. Echegoyen L. J. Am. Chem Soc. 2006, 128, 6626-6635.
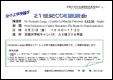 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE研究集会(No.1)が行われました。 【報告書】
第1回京都大学有機化学系COE合同シンポジウム 「精密有機合成の多様性と展望」
(小久見COEと斉藤COEによる共催シンポジウム)
日時:平成18年7月11日(火)10:00~17:40
場所:京都大学北部キャンパス理学研究科2号館第1講義室(120号室)
世話人:京都大学工学研究科材料化学専攻(小久見COE)
清水 正毅(tel:075-383-2444. shimizu
@npc05.kuic.kyoto-u.ac.jp)
京都大学理学研究科化学専攻(斉藤COE)
忍久保 洋(tel:075-753-4010. hshino
@kuchem.kyoto-u.ac.jp)
目的:精密有機合成化学は反応開発、天然物合成、高分子化学、材料化学、物性化学など様々な分野が密接に絡み合い大きく発展している。本シンポジウムでは第一線で活躍する若手研究者が、現在何を考え、どのように研究を進めているかについてお話し頂き、討論することにより、精密有機合成の多様な広がりを認識するとともに、その展望についても考える。
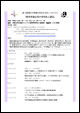 ←ポスター(プログラム)はこちら
←ポスター(プログラム)はこちら■21COE研究集会(No. 2)が行われました。
"Japan-France Advanced School for Functional Organic and Inorganic Materials
with Electrical Conductivity, Superconductivity, Ferromagnetism and Other Functions"
日時:平成18年7月16日(日)9:30~18:20
場所:京都大学百周年時計台記念館2階 国際交流ホールIII
世話役:京都大学理学研究科 化学専攻 陰山 洋 TEL:内線3991
化学専攻21COE事務局 植野 由美子 ueno @ kuchem.kyoto-u.ac.jp
案内:
当日参加も歓迎します。準備の都合がございますので、出来ますれば、ご参加ご希望の方は
ueno @ kuchem.kyoto-u.ac.jpまでご連絡ください。
資料:
1. プログラム 2. 講演要旨 3. ポスター発表 リスト 4. ポスター発表 要旨
■21COE講演会(No.21)が行われました。
日時:平成18年7月26日(水)14:00~16:30 【報告書】
講師:宍戸 宏造 教授(徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部)
演題:生物活性ハイブリッド天然物の合成
講師:長尾 善光 教授(徳島大学大学院ヘルスバイオサイエンス研究部)
演題:非共有結合相互作用を基盤とする不斉誘導反応
場所:京都大学化学研究所 共同研究棟 大セミナー室
連絡先:京都大学化学研究所 川端 猛夫 TEL:0774-38-3190
■21COE講演会(No.20)が行われました。
日時:平成18年8月1日(火)10:30~12:00 【報告書】
講師:Prof. L-J.Chen (National Tsing-Hua University, Taiwan)
演題:"In situ ultrahigh vacuum transmission electron microscope investigations
of nanostructures on silicon"
場所:京都大学化学研究所 新4階セミナー室(C-469号室)
連絡先:京都大学化学研究所 倉田 博基 TEL:内線3050
案内:
この度、L-J. Chen教授の講演を上記の要領で化学研究所にて開催いたします。
Chen教授の最近の研究対象は、薄膜プロセス、ナノ材料の合成、原子分解能電子顕微鏡分析、金属半導体の原子スケールダイナミックスなど多岐にわたっています。特にナノワイヤ、ナノドットなどの自己組織化、発光素子、メモリーなどへの物質創成と、超高真空電子顕微鏡による成長ダイナミクスの顕微鏡研究に優れた成果を上げておられます。
皆様にはお忙しいことと存じますが、是非お誘いの上多数のご来聴をお願いいたします。
 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.23)が行われました。
生存基盤科学研究ユニットとの共催による講演会 【報告書】
日時:平成18年8月3日(木)15:00~17:40
主題:Molecular Design for Exploring, Controlling, and Creating Biological Functions
場所:生存基盤科学研究ユニットオフィス(総合実験研究棟5階、宇治キャンパス)
プログラム:
15:00-15:40
講師:Prof. Andrew Woolley (Department of Chemistry, University of Toronto, Canada)
演題:Designing photo-controlled peptides and proteins
15:40-16:20
講師:Prof. Stefan Matile (Department of Organic Chemistry, University of Geneva, Switzrland)
演題:Synthetic multifunctional nanoarchitecture in lipid bilayer membranes:
Focus on artificial photosynthesis
16:35-17:15
講師:Prof. Jean Gariepy (Department of Medical Biophysics, University of Toronto, Canada)
演題:To live or not to live: Altering the fate of eukaryotic cells by designing cell-targeting
agents based on the unique protein architecture of the human tumor suppressor protein p53
17:15-17:40
講師:Dr. Naomi Sakai (Department of Organic Chemistry, University of Geneva, Switzrland)
演題:Counter anion mediated function of guanidinium-rich oligo-/polymers in model membranes
連絡先:京都大学化学研究所 川端 猛夫 二木 史朗 TEL:0774-38-3210
 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.22)が行われました。
日時:平成18年8月4日(金)16:00~18:00 【報告書】
講師:Prof. Stefan Matile (ジュネーブ大学、スイス)
演題:Rigid-Rod Nanoarchitecture in Lipid Bilayers: From Porous Sensors to Smart Photosystems
場所:京都大学理学研究科 理学6号館571号室
連絡先:京都大学理学研究科 化学専攻 大須賀 篤弘 TEL:内線4008
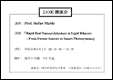 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.25)が行われました。
日時:平成18年8月9日(水)15:00~17:00 【報告書】
講師:Prof. Qian Xuhong (華東理工大学 学長、中国)
演題:Design, Synthesis and Application in Biological Area of Highly-selective
Fluorescent Molecular Sensor
場所:京都大学理学研究科 理学6号館303号室
連絡先:京都大学理学研究科 化学専攻 杉山 弘 TEL:内線4002
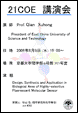 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.26)が行われました。
日時:平成18年8月14日(月)14:00~ 【報告書】
講師:Prof. Daniel I. Khomskii (Universitaet zu Koeln, Germany)
演題:Orbitally-driven superstructures and spin gaps in spinels and other oxides
場所:京都大学化学研究所 新4Fセミナー室
連絡先:京都大学化学研究所 無機先端機能化学 高野 幹夫 TEL:内線3120
内容:
Orbital degrees of freedom often lead to specific types of orbital and spin ordering. Complicated and interesting superstructures are observed in particular in B-sublattice of spinels. This is connected with the geometric frustration of this lattice and with the interconnection of edge-sharing MO6 octahedra, which is especially important for transition metals with partially-filled t2g levels. In some such systems (MgTi2O4, CuIr2S4, AlV2O4) there appears strange superstructures with the formation of spin gap states. In other cases (ZnV2O4) structural transitions, apparently connected with orbital ordering, are followed by long-range magnetic ordering. Last but not least, the famous Verwey transition in magnetite Fe3O4 leads to a very complicated structural pattern, accompanied by the appearance of ferroelectricity. In this talk I will discuss all these examples, paying main attention to an interplay of charge, spin and orbital degrees of freedom. In particular, for MgTi2O4, and CuIr2S4 we proposed the picture of orbitally-driven Peierls state [1], which can be also relevant for several other materials, such as NaTiO2, La4Ru2O10 [2] and some others. Orbital ordering can also give rise to a spontaneous formation of Haldane chains in a three-dimensional systems like pyrochlore Tl2Ru2O7 [4]. Finally, I propose the model of charge and orbital ordering in magnetite [4], which uses the idea of an interplay of site- and bond-centered ordering [5] and which seems to explain both the structural data and the presence of ferroelectricity in Fe3O4 below Verwey transition.
[1] D.I.Khomskii and T.Mizokawa, Phys.Rev.Lett. 94, 156402 (2005)
[2] Hua Wu et al., Phys.Rev.Lett. 96, 256402 (2006)
[3] Seongsu Lee et al., Nature Mater. 5, 471 (2006)
[4] D.I.Khomskii, unpublished
[5] D.V.Efremov, J.van den Brink and D.I.Khomskii, Nature Mater. 3, 853 (2004)
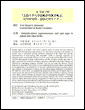 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.28)が行われました。
日時:平成18年8月22日(火)14:00 【報告書】
講師:Dr. Raivo Stern
(Director, National Institute of Chemical Physics & Biophysics, Estonia)
演題:Complex 2D Oxide BaCuSi2O6: A High Field NMR Study
場所:京都大学理学研究科6号館571号室
連絡先:京都大学理学研究科 化学専攻 吉村 一良 TEL:内線3989
概要:
最近注目されている2次元スピン系化合物における,ボーズアインシュタイン凝縮などの量子効果について高磁場下でのNMRによって研究した最新の結果について報告する.
 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.29)が行われました。
日時:平成18年8月23日(水)14:00 【報告書】
講師:Prof. Peter Lemmens
(Technical university of Braunschweig, Germany)
演題:Raman Scatterings in Strongly Correlated Electron Systems
場所:京都大学理学研究科6号館571号室
連絡先:京都大学理学研究科 化学専攻 吉村 一良 TEL:内線3989
概要:
Our present understanding of structure formation and response ofcorrelated electron systems to external fields is based on the firm belief in energy hierarchies and irrelevance of certain degrees of freedom. Competing interactions that often exist, e.g. as exchange paths in geometrically frustrated spin systems, however, lead to complex phase diagrams and low energy excitations with surprising properties. Further complexity may be induced by phase separation, domain formation and size effects. In the following we will discuss some examples of compounds that show structure formation or unusual collective behavior based on the coupling and competition of several degrees of freedom. A joint motive is a considerable complexity ofthe lattice or topology that allows an efficient coupling of phonon degrees of freedom to charge, spin or orbital states of transition metal ions.
 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.19)が行われました。
日時:平成18年8月23日(水)14:00~15:30 【報告書】
講師:Prof. Raynald Gauvin
(Department of Mining, Metals & Materials Engineering, McGill University, Canada)
演題:"X-Ray Microanalysis in the Electron Microscope"
場所:京都大学化学研究所 新4階(西)セミナー室(C-469号室)
連絡先:京都大学化学研究所 磯田 正二 TEL:内線3051
案内:
この度、R. Gauvin教授の講演会を上記のとおりの要領で化学研究所で開催いたします。
Gauvin教授の最近の研究対象は複合材料のX線微少分析で、特にモンテカルロシミュレーションによる定量解析の第一線で活躍されています。また、MicrobeamAnalysis Society of Americaの会長などを勤められ世界的に著名な研究者としてご活躍中です。
皆様にはお忙しいことと存知ますが、是非お誘いの上多数の御来聴をお願いいたします。
 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.27)が行われました。
日時:平成18年8月28日(月)15:30~17:00 【報告書】
講師:Prof. Jose L. Garcia-Ruano (Universidad Autonoma de Madrid, Spain)
演題:"Stereocontrolled Reactions Mediated by Remote Sulfoxides:
Formation and Reactivity of Enantiomerically Pure Benzylic Centers"
場所:京都大学化学研究所 共同研究棟大セミナー室
連絡先:京都大学化学研究所 川端 猛夫 TEL:0774-38-3190
案内:
Ruano教授は有機硫黄化学で著名な研究者で、特にスルホキシドを用いる不斉合成反応で顕著な業積をあげておられます。今回、第22回有機硫黄化学国際シンポジウム(埼玉)に招待講演者として出席のため来日されます。化学研究所ではキラルスルホキシドによる遠隔不斉誘導やキラルなベンジル位アニオンの化学についてご講演いただきます。多数の御来聴をお願い致します。
 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.30)が行われました。
日時:平成18年8月30日(水)14:00~15:30 【報告書】
講師:Prof. Ernst Schaumann (Technical University of Clausthal, Germany)
演題:Silicon Migration as a Useful Tool in Organic Synthesis
場所:京都大学化学研究所 4階 中会議室
連絡先:京都大学化学研究所 時任 宣博 TEL:0774-38-3200
案内:
E. Schaumann教授は、ケイ素、リン、硫黄などのヘテロ原子化学の専門家で、特に転位反応を活用した新規化合物の合成反応の開発で著名な研究者です。今回、埼玉で開催される第22回有機硫黄化学国際シンポジウムの国際組織委員および招待講演者として来日されるのを機会に、化学研究所でのご講演をお願い致しました。有機合成化学の有名なハンドブックであるScience of Synthesisの編者のお一人としても活躍されています。ご多忙中とは存じますが、お誘い合わせの上多数の皆様のご来聴をお願い致します。
 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE研究集会(No.3)が行われました。
「各種顕微鏡と極微細加工、操作で拓く化学、工学、生物学」 【報告書】
日時:平成18年9月5日(火)10:00~17:40
場所:京都大学百周年時計台記念館2階 国際交流ホールIII
世話人:京都大学理学研究科 化学専攻 熊崎 茂一
連絡先:tel. 075-753-4023, kumazaki @ kuchem.kyoto-u.ac.jp
協賛:分光学会関西支部
案内:
ナノテクノロジーと喧伝されている今日、確かに各種顕微鏡や関連した極微細操作、加工技術が広範な物質科学に変革をもたらしている。 研究対象によって細分化された学会もあるが、本会議では敢えて、技術的共通性が高いが日頃異なる学会で語られる講演を一堂に集結させることを試みた。単一分子やナノ-サブマイクロレベルの構造の直接観察、操作、加工の進展とそれらを応用した生物まで含めた広い物質科学への応用について理解し、大局観が得られることを希望している。
●研究者のみならずこれから進路を決める若い学生にも聴講が有意義であると期待している●
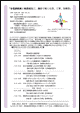 ←ポスター(プログラム)はこちら
←ポスター(プログラム)はこちら■21COE研究集会(No.4)が行われました。
第三回京都大学化学系21世紀COE合同シンポジウム
「低温合成法による新機能性材料の創製」 【報告書】
日時:平成18年9月8日(金)10:30~17:10
場所:京都大学工学部物理系校舎312号室(吉田地区)
世話人:京都大学大学院理学研究科化学専攻 陰山 洋(斉藤COE)
Tel: 075-753-3991, kage @ kuchem.kyoto-u.ac.jp
京都大学大学院工学研究科材料工学専攻 邑瀬 邦明(小久見COE)
Tel: 075-753-9132, kuniaki.murase @ a0017299.mbox.media.kyoto-u.ac.jp
概要:
20世紀は石油の時代と言われた。石油化学をもとに有機化学はめざましく発展し、我々の生活を豊かにした。しかし他方、機能性材料に目を向けると、我々の身の回りは様々な無機化合物で溢れている。蛍光材料、光学材料、センシング材料、磁性材料、電子材料、電池活物質、固体触媒材料、誘電材料、‥‥。機能性材料の主役は無機物質なのである。無機物質の合成には、高温での固相反応法のかわりに、インターカレーション、ゾル−ゲル法、液相析出法、電気化学的手法など、投入するエネルギーが小さい低温合成法が近年では幅広く、積極的に使われるようになってきた。このような低温合成をさらに深く追求することは、自然順応型の新しい機能性材料プロセスの開拓につながる。しかしながら、無機材料を興味の対象とする研究者は化学、材料工学、金属工学、電気・電子工学など多分野にわたっており、異なる分野間で交流する機会が有機化学に比べて希薄である。このシンポジウムでは、様々な分野の無機化学者に研究内容をお話しいただき、自由な討論を通じて、主として低温合成手法に関する知識を習得(共有)し、さらに新たな研究の方向性を探るのが目的である。
 ←プログラムはこちら
←プログラムはこちら■21COE講演会(No.32)が行われました。
日時:平成18年10月4日(水)15:00~16:30 【報告書】
講師:Prof. Francesco A. Devillanova
(Departimento di Chimica Inorganica ed Analitica,Univerdita' degli Studi di Cagliari, Italy)
演題:The nature of the chemical bond in linear three-body systems:
from I3- to mixed chalcogen/halogen and trichalcogen moieties.
場所:京都大学化学研究所 新4階セミナー室(C-469)
連絡先:京都大学化学研究所 時任 宣博 TEL:内線3200
小澤 文幸 川端 猛夫 中村 正治 村田 靖次郎
案内:
F. A. Devillanova教授は、硫黄・セレン・ハロゲン元素などのヘテロ原子化学の専門家で、幅広い研究分野に貢献されています。特に最近ではカルコゲン元素と、遷移金属あるいはハロゲン元素間でのドナー/アクセプター相互作用の研究で成果をあげていらっしゃいます。今回、福岡で開催される第18回基礎有機化学連合討論会の招待講演者として来日されるのを機会に、化学研究所でのご講演をお願い致しました。ご多忙中とは存じますが、お誘い合わせの上多数の皆様のご来聴をお願い致します。
 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.24)が行われました。
第三回化学教室卒業生・企業研究開発-成功への道-
日時:平成18年10月6日(金)16:30~
講師:皆地 良彦 先生
(TDK株式会社テクノロジーGrp基礎材料開発センター 磁石材料グループ研究主任)
演題:世界最強フェライト磁石の開発
場所:京都大学理学研究科 理学2号館第1講義室
連絡先:京都大学大学院理学研究科化学専攻
陰山 洋 TEL:内線3991 大須賀 篤弘 TEL:内線4008
案内:
二年前より大須賀教授の発案で,企業で活躍されている化学教室出身の方の講演会を開催しています.一昨年の講演者は,光物理研究室出身の浜田恵美子氏(太陽誘電:「CD-R、世界初の一枚との出会い」),昨年の講演者は,有機化学研究室出身の大口正勝氏(東洋紡:「企業の研究開発 - もの作りに魅せられて」)と芳賀隆弘氏(石原産業:「新薬開発のためのトリフルオロメチルピリジン化学」)でした.
今年度は,金相学研究室出身(1993年)で,現在(株)TDKの研究主任・皆地良彦氏に依頼しました.皆地氏によって開発されたフェライト(鉄の酸化物)磁石は,従来型フェライト磁石より遥かに強力(世界最強)で,かつ鉄は安価なため,現在,車や家電製品にいたる産業界の幅広い分野で使用されています.企業研究の面白さや苦労話についてお話ししていただく予定です.皆様,是非ご参加ください.
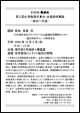 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.31)が行われました。
日時:平成18年10月10日(火)14:45~ 【報告書】
講師:Prof. Carsten Bolm (RWTH-Aachen, Germany)
演題:New ligands for asymmetric metal catalysis
場所:京都大学理学研究科 理学2号館129講義室
連絡先:京都大学大学院理学研究科 化学専攻 林 民生 TEL:内線3983
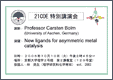 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.33)が行われました。【報告書】
日時:平成18年10月11日(水)
講師:Prof. Gerard Simonneaux (レンヌ大学, フランス)
演題:Asymmetric Homogeneous and Heterogeneous Reactions Catalyzed by Metalloporphyrins
場所:京都大学理学研究科 理学6号館571講義室
連絡先:京都大学大学院理学研究科 化学専攻 大須賀 篤弘 TEL:内線4008
 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.35)が行われました。
日時:平成18年10月20日(金)15:00~ 【報告書】
講師:Prof. Yinsheng Wang (University of California at Riverside, USA)
演題:Chemistry and Biology of Novel Oxidative Intrastrand Crosslink Lesions of DNA.
場所:京都大学理学研究科 理学2号館第1講義室(130号室)
世話人:京都大学理学研究科 化学専攻 杉山 弘 TEL:内線4002
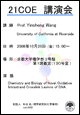 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE研究集会(No.5)が行われました。
第3回有機元素化学セミナー 【報告書】
日時:平成18年10月26日(木)10:00~
場所:京都大学化学研究所 共同研究棟大セミナー室
参加申込・問合せ先:京都大学化学研究所 時任 宣博・小澤 文幸・笹森 貴裕・長洞 記嘉
ご案内:プログラム、参加申し込み方法は下のポスター(開催案内)をご覧下さい。
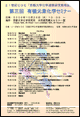 ←ポスター(開催案内)はこちら
←ポスター(開催案内)はこちら■21COE講演会(No.36)が行われました。
日時:平成18年10月27日(金)14:00~15:30 【報告書】
講師:宮崎 州正 先生(高知工科大学)
演題:ガラス転移と動的相関長
場所:京都大学工学研究科 A2棟307号室
世話人:京都大学工学研究科 分子工学専攻 佐藤 啓文
要旨:ガラス転移は、(見かけ上)熱力学的な異常や巨視的な長距離相関を示さずに、緩和時間だけが巨視的に発散する、まことに不思議な現象です。しかし、ガラス転移のスローダイナミクスに、協同現象に特徴的な相関長が隠されていることは古くから予想されておりました。その相関長を実際に捕らえることできるようになったのは、ようやく1990年代も後半に入ってからです。そのころ、特にシミュレーションによって、過冷却液体中に動的に不均一な構造が見られること、そしてその不均一な構造がガラス転移点に近くなるにつれて成長することが、明らかになってきました。私たちは、モード結合理論を拡張して、平均場理論の枠組みになかで、相関長を計算することに成功しました。ガラス転移のあらゆる理論において、相関長を第一原理的に導出したのは、これが初めてのことです。
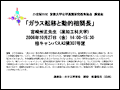 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.34)が行われました。
日時:平成18年10月30日(月)14:00~ 【報告書】
講師:Prof. Dominique de Caro
(Laboratoire de Chimie de Coordination du CNRS, Universite Paul Sabatier, Toulouse, France)
演題:Thin Films and Nano-wires of Molecular Materials: Preparation and Characterization
場所:京都大学理学研究科 理学6号館303講義室
連絡先:京都大学低温物質科学研究センター 矢持 秀起 TEL:内線4036
案内:
上記表題でのde Caro博士の講演会の後、引き続き、LTM博士研究員 中野 義明 博士による、"EDO-TTF の陽イオンラジカル塩における同位体効果"(英語講演)の講演も予定しております(LTMセミナーとして開催)。
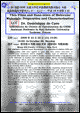 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.37)が行われました。
日時:平成18年10月31日(火)14:45~ 【報告書】
講師:Prof. Scott Eric Denmark (University of Illinois, USA)
演題:Silicon-Based Cross-Coupling Reactions:
A Practical Alternative to Boron- and Tin-Based Methods
場所:京都大学理学研究科 理学2号館129講義室
連絡先:京都大学理学研究科 化学専攻 林 民生 TEL:内線3983
 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.42)が行われました。
日時:平成18年11月7日(火)14:45~ 【報告書】
講師:Prof. Shengming Ma (Shanghai Institute of Organic Chemistry (SIOC), China)
演題:Development of New reactions based on Cyclometallation of Bisallenes
場所:京都大学理学研究科 理学2号館129講義室
連絡先:京都大学理学研究科 化学専攻 林 民生 TEL:内線3983
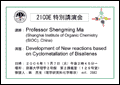 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.41)が行われました。 【報告書】
(主催:斉藤COE、共催:京都大学工学研究科「化学教育トリニティ」プログラム)
日時:平成18年11月9日(木)16:00~17:00
講師:Prof. Lars Baltzer (Dep. of Biochem. and Organic Chem., Uppsala University, Sweden)
演題:Polypeptide conjugates as high-affinity binders for proteins
場所:京都大学工学研究科 桂キャンパスA2棟303号室
連絡先:京都大学工学研究科 合成・生物化学専攻 浜地 格 TEL:内線2754
案内:Baltzer教授はデザインペプチドの分野で活躍されている世界第一線の研究者です。特定のタンパク質と強く相互作用するペプチドの設計に関して講演頂きます。
ご来聴を歓迎します。
 ←ポスター(COE)
←ポスター(COE)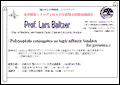 ←ポスター(トリニティ)
←ポスター(トリニティ)■21COE講演会(No.44)が行われました。
日時:2006年11月9日(木) 16:30-18:00
講師:今中 忠行 教授(京都大学工学研究科 合成・生物化学専攻)
演題:南極観測隊に参加して
場所:6号館講義棟4階402講義室
連絡先:京都大学理学研究科 化学専攻 三木 邦夫 TEL:内線4029
案内:
構造生物学・構造ゲノム科学の分野で、私たちの研究室と共同研究していただいている工学研究科の今中忠行先生は、2004年11月末から3月末まで、第46次南極観測隊に参加され、南極での極限環境で成育する微生物を採取され、現在、その遺伝子の同定・解析を行っておられます。今回のご講演では、ご研究の成果のみならず、南極でのご体験や美しい南極の風景も交えてお話しいただきますので、ご専門の異なる方々や、学生諸君のご来聴も歓迎いたします。
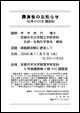 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.46)が行われました。
日時:平成18年11月9日(木)15:30~17:00 【報告書】
講師:Prof. Shengming Ma (上海有機化学研究所、中国)
演題:Control of Regio-and Stereoselectivity of Electrophilic Addition of Allenes
場所:京都大学化学研究所 共同研究棟大セミナー室
連絡先:京都大学化学研究所
時任 宣博、小澤 文幸、中村 正治、村田 靖次郎、川端 猛夫 TEL:内線3190
案内:
Ma 教授は有機金属触媒を用いる有機合成化学がご専門で、昨年ジュネーブで開催されたOMCOS-13でThieme Award を授賞した新進気鋭の研究者です。また、40代前半にしてChinese Academy of Scienceのメンバーに選ばれるなど、中国を代表する科学者です。今回、IKCOC-10 に招待講演者として来日される機会に化研でも講演していただけることになりました。多数の皆様のご来聴を歓迎いたします。
 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.49)が行われました。
日時:平成18年11月9日(木)14:00~15:30
講師:Prof. Martin Kotora (Department of Organic and Nuclear Chemistry, Faculty of Science,
Charles University in Prague, Czech Republic)
演題:Relation between cleavage and formation of C-C bonds
場所:京都大学化学研究所 共同研究棟 大セミナー室
連絡先:京都大学化学研究所 中村 正治 TEL:0774-38-3180
案内:
Kotora 教授は有機金属錯体化学および有機合成化学がご専門です。
1993年から3年間,分子科学研究所にて高橋保先生,さらに1995年から2年間,米国Purdue大学で根岸英一先生の下で博士研究員をされた後,北海道大学で4年間助教授をされました。その後,チェコに戻られて現在のポジションを得られています。炭素ー炭素結合の開裂と再生成の制御という内容で最新の成果をご講演くださる予定です。
なお本講演会はShengming Ma先生との講演会とのジョイントセミナーの形式で行います。
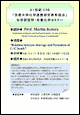 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.40)が行われました。 【報告書】
(主催:斉藤COE、共催:京都大学工学研究科「化学教育トリニティ」プログラム)
日時:平成18年11月10日(金)16:30~
講師:Prof. Roeland J. M. Nolte (Radboud University Nijmegen, The Netherlands)
演題:From Single-Molecule to Supramolecule Catalysis
場所:京都大学工学研究科 A2棟308号室
連絡先:京都大学工学研究科 合成・生物化学専攻 吉田 潤一 TEL:内線2726
案内:
Professor Nolte’s research interests span a broad range of topics at the interfaces of supramolecular chemistry, macromolecular chemistry, and biomimetic chemistry. He focuses on the design of catalysts and (macro) molecular materials. He and his group have published over 500 scientific papers!
http://www.orgchem.science.ru.nl/research/nolte.htm
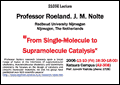 ←ポスター(COE)
←ポスター(COE)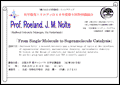 ←ポスター(トリニティ)
←ポスター(トリニティ)■21COE講演会(No.50)が行われました。
日時:平成18年11月16日(木)13:30~15:00
講師:Prof. Peter G. Schultz (The Scripps Research Institute, U.S.A.)
演題:New Opportunities at the Interface of Chemistry and Biology
場所:京都大学農学部 W100教室
連絡先:化学研究所 分子微生物科学 江崎 信芳 TEL:0774-38-3240
 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.43)が行われました。
日時:平成18年11月17日(金)16:30~ 【報告書】
講師:Prof. Hans-Ulrich Reissig (Freie Universität Berlin, Germany)
演題:Synthesis of Heterocycles via Metalated Alkoxyallenes
場所:京都大学理学研究科 理学2号館129講義室
連絡先:京都大学理学研究科 化学専攻 林 民生 TEL:内線3983
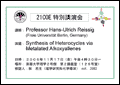 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.45)が行われました。
日時:平成18年11月20日(月)16:00~ 【報告書】
講師:Prof. Pierre D. Harvey (Université de Sherbrooke, Canada)
演題:Through Space Energy Transfer: The Photoprocess of Life
場所:京都大学理学研究科 理学6号館571号室
連絡先:京都大学理学研究科 化学専攻 大須賀 篤弘 TEL:内線4008
 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.51)が行われました。
日時:平成18年11月20日(月)14:00~ 【報告書】
講師:鈴村 順三 教授 (名古屋大学大学院理学研究科物質理学専攻)
演題:有機導体における多様な電子状態と超伝導
場所:理学研究科 理学6号館204号室
連絡先:低温物質科学研究センター 矢持 秀起 TEL:内線4036
案内:
多くの有機導体が化学的に合成され興味深い物理が展開されてきた。常圧での状態の他に、高圧、高磁場、低温の環境下で、擬1次元導体から擬2次元導体へ、絶縁体から超伝導へと移り変わるさまざまな電子状態が出現してきた。この物質では骨格となる平坦な分子の構造や空間的な配置の多様性が電子の伝導性に影響している。分子の積層方向や分子間距離が電子状態に顕著な効果をもたらし、通常の固体金属では予想できない新しい電子状態が観測されている。最近、θ型やα型のBEDT-TTF塩で長距離クーロン斥力が原因で生じる電荷秩序が観測され話題となっている。さらにこれらの有機導体で加圧等により超伝導も出現している。これらの原因として、電子間クーロン相互作用は勿論であるが、分子間の電子のトランスファーが原因で生じる電荷不均化が重要な役割を果たしている。単位胞に4つのBEDT-TTF分子が存在するα型の塩においてアニオンの置換や一軸加圧により出現するディラック粒子や、スピンや電荷揺らぎを媒介とした超伝導を紹介する。
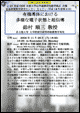 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.47)が行われました。 【報告書】
(主催:斉藤COE、共催:京都大学工学研究科「化学教育トリニティ」プログラム)
日時:平成18年11月22日(水)16:30~18:00
講師:Dr. Irena G. Stara (Institute of Organic Chemistry and Biochemistry,
Academy of Science of the Czech Republic, Prague, The Czech Republic)
演題:Chemistry of Helicenes and Their Congeners
場所:京都大学桂キャンパス、A2棟-303号室
連絡先:京都大学工学研究科 合成・生物化学専攻 吉田 潤一 E-mail:yoshida*
*sbchem.kyoto-u.ac.jp
案内:
Dr. Stara is a senior scientist and a project leader of the group of organic synthesis.
Recently, an original approach to helicene frameworks by using transition metal catalysis has been developed by her group. The preparation and use of helicenes and their congeners will be discussed.
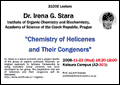 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.48)が行われました。 【報告書】
(主催:斉藤COE、共催:京都大学工学研究科「化学教育トリニティ」プログラム)
日時:平成18年12月1日(金)15:30~17:00
講師:Professor David Crich (University of Illinois at Chicago, Chicago, USA)
演題:Diastereoselective Glycosylation: Recent Advances
場所:京大桂キャンパス、A2棟-302号室
連絡先:京都大学工学研究科 合成・生物化学専攻 吉田 潤一 E-mail:yoshida*
*sbchem.kyoto-u.ac.jp
案内:
Professor Crich’s researches interests include the fields of synthetic organic chemistry such as organic synthesis using radical reactions and carbohydrate syntheses. Especially, his recent contributions to the development of new methodologies for synthetic carbohydrates are outstanding!
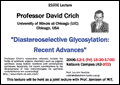 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE研究集会(No.6)が行われました。
京都大学生化学系COE合同シンポジウム 【報告書】
「生命現象の起源を司る生体高分子の化学~DNA, RNA, Proteinの機能構造とその制御~」
日時:平成18年12月2日(土)13:00~17:25
場所:京都大学理学研究科 理学2号館第1講義室(120号室)
世話人:
京都大学大学院理学研究科化学専攻(齋藤COE)
板東俊和 (tel:075-753-4001: bando*)
藤橋雅宏 (tel:075-753-4030: mfuji*)
京都大学大学院生命科学研究科(米原COE)
齊藤博英 (tel:075-753-3997: h-saito*)
*kuchem.kyoto-u.ac.jp
目的:
最近のゲノムプロジェクト完了と分子生物学の急速な進歩によって、生命現象の起源を司るDNA、RNA、Proteinを初めとした、生体高分子の化学に関する研究が大きく展開している。本シンポジウムでは、第一線で活躍する若手研究者が、現在、どのようにこの領域の研究を進めているか討論することにより、生命科学分野の多様な広がりを認識するとともに、DNA, RNA, Protein研究の展望を考える。
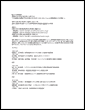 ←プログラムはこちら
←プログラムはこちら■21COE講演会(No.38)が行われました。
日時:平成18年12月5日(火)15:00~ 【報告書】
講師:Dr. Jon T. Hougen (National Institute of Standards and Technology, USA)
演題:Introduction to Vibration-torsion-rotaiton interactions
in the lowest vibrational fundamental of acetaldehyde.
場所:京都大学理学研究科 理学6号館302講義室
連絡先:京都大学理学研究科 化学専攻 馬場 正昭 TEL:内線6834
 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.52)が行われました。
(主催:斉藤COE、共催:京都大学工学研究科「化学教育トリニティ」プログラム)
日時:平成18年12月13日(水)15:00~16:30
講師:Prof. David H. Thompson (Purdue University)
演題:Development of Bioresponsive Materials for Drug Delivery
and Integral Membrane Protein Sensing
場所:京都大学桂キャンパス A2棟3階305号室
連絡先:京都大学工学研究科 合成・生物化学専攻 青山 安宏 TEL:内線2766
案内:Thompson教授はドラッグデリバリーやセンシング関係で著名な研究者であり、現在JSPS(日本学術振興会)招聘教授として滞在しておられます。ご来聴をお願いします。
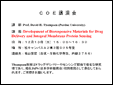 ←ポスター(COE)
←ポスター(COE)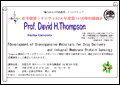 ←ポスター(トリニティ)
←ポスター(トリニティ)■21COE講演会(No.54)が行われました。 【報告書】
日時:平成18年12月14日(木)
講師:Prof. Karl M. Kadish (University of Houston, USA)
演題:New Insights Into the Electrochemistry of Porphyrins,
Phthalocyanines and Related Hybrid Molecules
場所:理学研究科2号館129号室
連絡先:京都大学理学研究科 化学専攻 大須賀 篤弘 TEL:内線4008
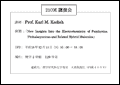 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE研究集会(No.7)が行われました。 【報告書】
第2回京都大学有機化学系COE合同シンポジウム
「精密有機合成の多様性と展望」
日時:平成18年12月15日(金)10:00~16:50
場所:京都大学桂キャンパスBクラスター桂ホール
参加費:無料
世話人:京都大学工学研究科物質エネルギー化学専攻(小久見COE)
近藤 輝幸(tel:075-383-2508. teruyuki*)
京都大学理学研究科化学専攻(斉藤COE)
白川 英二(tel:075-753-3985. shirakawa**)
*scl.kyoto-u.ac.jp
**kuchem.kyoto-u.ac.jp
目的:
精密有機合成化学は反応開発、天然物合成、高分子化学、材料化学、物性化学など、様々な分野が密接に絡み合い大きく発展している。本シンポジウムでは、第一線で活躍する若手研究者が、現在何を考え、どのように研究を進めているかについてお話し頂き、討論することにより、精密有機合成の多様な広がりを認識するとともに、その展望について考える。
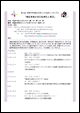 ←プログラムはこちら
←プログラムはこちら■21COE講演会(No.56)が行われました。
日時:平成19年1月11日(木)14:00~15:00
講師:腰原 伸也 教授 (東京工業大学理工学研究科)
演題:レーザー・放射光結合計測が生み出す新しい物質科学
場所:理学研究科6号館571号室
連絡先:京都大学理学研究科 化学専攻 安藤 耕司 TEL:内線4020
案内:
「物質の構造」と「性質(物性)」の関連の解明、ならびにその研究のために用いる技術開拓は、物質科学に共通する最も基本的テーマである。しかしながら、光励起状態のような高いエネルギー状態にある凝縮系物質、ましてや動的に構造が変化したり揺らいだりしているものに関しては、技術開発に適したデモンストレーション用物質が無いこともあって、一部孤立分子を除くと「励起状態の物質構造」と「物性」という視点での研究は、今日に至るもほとんど皆無なのが現状である。ところが昨今の大型放射光光源とパルスレーザー光の組み合わせ技術の進展、高強度超短パルスレーザーによるX線発生技術の進歩、さらには高感度2次元X線検出器の導入によって、ピコ秒時間スケールはもとより、場合によってはフェムト秒スケールの構造変化を、オングストロームスケールでとらえることすら可能となってきた。我々はつい最近、この種の装置を用いて、電荷移動錯体における光誘起強誘電性発現の、ミクロ機構解明のための手がかりを得ることに成功した。加えて、結晶のみならず溶液等の不規則系においても、物質系を適宜選択すれば時間分解構造解析が可能となるような技術も登場するに至っている。以上の背景に基づき本講演では、時間分解構造解析技術の動向ならびにその物質科学的意味合いを実例も交えながら解説する。
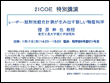 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.53)が行われました。
日時:平成19年1月15日(月)14:45~ 【報告書】
講師:Dr. Lutz Ackermann (The Ludwig-Maximilians-Universität München, Germany)
演題:Metal-Catalyzed Coupling Reactions:
From Air-Stable HASPO Preligands to C-H Bond Activations
場所:理学研究科2号館第2講義室(129号室)
連絡先:京都大学理学研究科 化学専攻 林 民生 TEL:内線3983
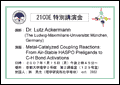 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.55)が行われました。
日時:平成19年1月22日(月)14:45~ 【報告書】
講師:Prof. Clark R. Landis (University of Wisconsin-Madison, USA)
演題:3,4-Diazaphospholanes and Highly Active
and Enantioselective Hydroformylation Catalysts
場所:理学研究科2号館第2講義室(129号室)
連絡先:京都大学理学研究科 化学専攻 林 民生 TEL:内線3983
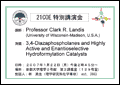 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.57)が行われました。 【報告書】
(主催:斉藤COE、共催:京都大学工学研究科「化学教育トリニティ」プログラム)
日時:平成19年1月22日(月)10:30~12:00
講師:Prof. Russel F. Howe (University Aberdeen, U.K.)
演題:Semiconducting Zeolites as Nanostructured Photocatalysts ?
場所:桂キャンパス A2棟 304号室
連絡先:京都大学工学研究科 分子工学専攻 田中 庸裕 TEL:内線2558
案内:
Zeolites which contain semiconducting oxides as part of their structural framework offer potential advantages as photocatalysts: the semiconductor component has a well defined nanostructure, and the zeolite pore system allows convenient access of reactant molecules. This lecture will consider whether these advantages can be realised in practice with the titanosilicates ETS-10, ETS-4, TSP and the vanadosilicate AM-6.
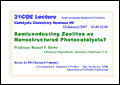 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE研究集会(No.8)
「2007年KAIST-京都大学化学シンポジウム」が行われました。
日時:平成19年1月26(金)16:30~18:00
平成19年1月27(土)8:30~19:00
場所:京都大学福井謙一記念研究センター3階大会議室
世話役:韓国科学技術院 Hyotcherl Ihee
京都大学理学研究科 化学専攻 丸岡 啓二・谷村 吉隆
※問い合わせは谷村(tanimura*)までお願いします。
案内:当日参加も歓迎します。準備の都合がございますので、事前登録をお願いします。ご参加ご希望の方は氏名、所属、職種(学生の方は学年)を21COE事務局の植野(ueno*)までご連絡ください。 (*kuchem.kyoto-u.ac.jp)
Abstracts (NEW! 1/14 更新)
Poster#
ProgramSchedule
"2007 KAIST-Kyoto University Chemistry Symposium"
| Date and Time: | January 26, 2007 (Fri.) 16:30~18:00 January 27, 2007 (Sat.) 8:30~:19:00 |
| Place: | Fukui Institute for Fundamental Chemistry, Kyoto University http://www.fukui.kyoto-u.ac.jp/access-e.htm |
| Language: | English |
| Organizers: | Hyotcherl Ihee, KAIST Keiji Maruoka and Yoshitaka Tanimura, Kyoto University Please address any inquires to Prof. Y. Tanimura at tanimura*. |
| Registration: | There will be no registration fees. On-site registrations are available. Participants are encouraged to pre-register. Send your name, affiliation, title to the Symposium Secretariat at ueno* for registration. |
■21COE講演会(No.59)が行われました。
日時:平成19年2月5日(月)17:00~18:00
講師:天能 精一郎 助教授 (名古屋大学大学院情報科学研究科)
演題:相関因子を用いた分子軌道法の開発
場所:理学研究科6号館571号室
連絡先:京都大学理学研究科 化学専攻 谷村 吉隆 TEL:内線4017
案内:
動的電子相関は、主配置の違いを通じて反応熱や励起エネルギーに直接影響を与える重要な効果であるが、電子間に存在するカスプのために一電子基底関数展開の収束が非常に遅いことが知られている。本講演では、従来の一電子基底関数に加えて、二電子基底関数であるジェミナル基底を用いた高精度分子軌道法を紹介する。特に、私たちが最近提案したSlater型ジェミナルの有効性を中心に分野の動向を述べる。
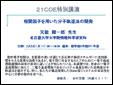 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.60)が行われました。 【報告書】
日時:平成19年2月13日(火)
講師:Prof. Albert Sun-Chi Chan (The Hong Kong Polytechnic University, China)
演題:Catalytic asymmetric C-C bond formation
場所:理学研究科2号館第2講義室(129号室)
連絡先:京都大学理学研究科 化学専攻 林 民生 TEL:内線3983
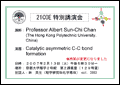 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.58)が行われました。
日時:平成19年2月16日(金)13:30~14:30
講師:笹井 理生 教授 (名古屋大学大学院工学研究科)
演題:遺伝子スイッチの確率ダイナミクス
場所:理学研究科6号館571号室
連絡先:京都大学理学研究科 化学専攻 谷村 吉隆 TEL:内線4017
案内:
細胞はメゾスコピックな系であり、細胞ひとつに含まれる転写制御タンパク質やDNAの 分子数は小さい。このため、遺伝子の発現はゆらぎを伴う確率過程であると考えられている。遺伝子発現ダイナミクスの理論を紹介し、DNAの状態変化が頻繁でないときに生じる異常に遅い緩和を議論する。また、転写制御とともに転写後のタンパク質相互作用による制御を含むシステムとして酵母の細胞周期を制御する生体分子ネットワークのモデルを解析し、ゆらぎに対して頑健なネットワークのデザインを考える。
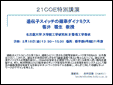 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.61)が行われました。
日時:平成19年2月16日(金)14:30~15:30
講師:原田 崇広 先生 (福井大学工学部知能システム工学科)
演題:非平衡Langevin系における揺らぎのエネルギー論
場所:理学研究科6号館571号室
連絡先:京都大学理学研究科 化学専攻 安藤 耕司 TEL:内線4020
案内:
非平衡定常状態にある系においては、外界から供給されるエネルギーが環境に散逸される事によってエネルギー収支がバランスしている。従って、そうしたエネルギーの流れを実験的に特徴づけることは非平衡系の特性を調べるための重要なステップである。
もし系が平衡近傍にあるならば、既に線形非平衡熱力学の枠組みがあるので、実験的に測定可能な量を元にエネルギーの流れを決定することが可能である。しかしながら、系が平衡から離れるにつれて系の個性が顕在化してくるため、エネルギーの流れを決定するためには、系の詳細に立ち入った議論が必要になる。
ところが我々は最近、非平衡系において、単位時間当たりのエネルギー散逸率が、その系の揺動散逸関係の破れの度合いと直接結びついていることを見いだした。揺動散逸関係は、巨視的な変数の揺らぎと摂動に対する応答とを結びつける関係式で、平衡状態では成立するが、非平衡定常状態では成り立っていない。
我々の得た結果によると、非平衡状態にある系の遅い自由度については、その揺動散逸関係の破れを測定することによって、系の詳細に立ち入ることなく、エネルギー散逸率を見積もることができる。
この結果は、Langevin方程式で記述されるような系であれば、非線形非平衡領域でも成立し、また種々の一般化も可能である。
講演では、以上の結果の詳細を述べ、また生体分子モーターの機能解析への応用を提案したい。
【参考文献】
[1] T. Harada and S.-i. Sasa, Phys. Rev. Lett 95, 130602 (2005).
[2] T. Harada and S.-i. Sasa, Phys. Rev. E 73, 026131 (2006).
[3] T. Harada and S.-i. Sasa, Math. Biosci. in press; cond-mat/0610757.
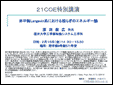 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE研究集会(No.9)が行われました。 【報告書】
京都大学化学系21世紀COE合同シンポジウム
「低温合成法による新機能性材料の創製」
日時:平成19年2月20日(火)10:30~17:10
場所:京都大学化学研究所大セミナー室(宇治地区・共同研究棟1F)
http://www.kuicr.kyoto-u.ac.jp/kaken_map1.html
連絡先:京都大学化学研究所 山本 真平(斉藤COE)
Tel: 0774-38-4718 mail: shinpei*
*msk.kuicr.kyoto-u.ac.jp
概要:
20世紀は石油の時代と言われた。石油化学をもとに有機化学はめざましく発展し、我々の生活を豊かにした。しかし他方、機能性材料に目を向けると、我々の身の回りは様々な無機化合物で溢れている。蛍光材料、光学材料、センシング材料、磁性材料、電子材料、電池活物質、固体触媒材料、誘電材料、‥‥。機能性材料の主役は無機物質なのである。無機物質の合成には、高温での固相反応法のかわりに、インターカレーション、ゾル−ゲル法、液相析出法、電気化学的手法など、投入するエネルギーが小さい低温合成法が近年では幅広く、積極的に使われるようになってきた。このような低温合成をさらに深く追求することは、自然順応型の新しい機能性材料プロセスの開拓につながる。しかしながら、無機材料を興味の対象とする研究者は化学、材料工学、金属工学、電気・電子工学など多分野にわたっており、異なる分野間で交流する機会が有機化学に比べて希薄である。このシンポジウムでは、様々な分野の無機化学者に研究内容をお話しいただき、自由な討論を通じて、主として低温合成手法に関する知識を習得(共有)し、さらに新たな研究の方向性を探るのが目的である。
 ←プログラムはこちら
←プログラムはこちら◆最終年度 報告会◆が行われました。
日時:平成19年2月22日(木)9:30~
場所:京都大学時計台記念館2F国際交流ホールⅢ
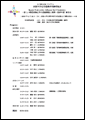 ←プログラムはこちら
←プログラムはこちら■21COE講演会(No.63)が行われました。 【報告書】
日時:平成19年3月1日(木)16:00~17:00
講師:Prof. Kee Hag Lee (Department of Bionano Chemistry, Wonkwang University, Korea)
演題:Structure, Reactivity, and Dynamics of Fullerene Clusters: Computational Study
場所:工学研究科A2棟303号室(桂キャンパス)
連絡先:京都大学工学研究科 分子工学専攻 田中 一義 TEL:内線2549
案内:
気相中のフラーレンクラスターの反応部位は、反応速度定数の実験値とフロンティア分子軌道の福井関数を組み合わせて解釈できることを示す。またフラーレン2量体は人工光合成、新規分子系の電子デバイス、超分子化学などに関連して興味深いが、ここでは荷電フラーレン2量体の構造及び電子的性質についての理論的な解析結果を紹介する。さらにフラーレン2量体の相対的な安定性が、電荷とスピン状態のカップリングによって説明できることも示す予定である。
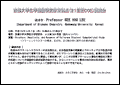 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.64)が行われました。 【報告書】
日時:平成19年3月6日(火)15:30~
講師:Dr. Wang-Yau Cheng (IAMS, Taipei, Taiwan)
演題:High-resolution Laser Spectroscopy for Wavelength Standard and Frequency Comb
場所:理学研究科6号館204号室
連絡先:京都大学理学研究科 化学専攻 馬場 正昭 TEL:内線6834
 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.62)が行われました。
日時:平成19年3月9日(金)15:00~17:00
講師:住 斉 先生 (筑波大学名誉教授)
演題:「光合成研究からミトコンドリアDNA解析へ:飛騨びとのルーツは本土縄文人」
場所:理学研究科6号館571号室
連絡先:京都大学理学研究科 化学専攻 谷村 吉隆 TEL:内線4017
案内:
呼吸は光合成の逆反応で、外から取り入れた酸素ガスで栄養物を酸化することにより生体エネルギーを得て炭酸ガスを捨てる機能である。それを行うミトコンドリアは人の細胞中にも存在する。ミトコンドリアは独自のDNAを持ち、それの解析によりこの10年ほどの間に現世人類のルーツに関して革命的事実が明らかにされて来た。この解析を演者の郷里である飛騨に適用した結果、飛騨びとのルーツは、縄文人の代表たる本土型縄文人であり、弥生人がおよそ2500年前に朝鮮半島を経て大挙して日本に入って来る前から日本にいた原日本人であることが判りつつある。
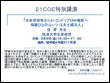 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.65)が行われました。
日時:平成19年3月10日(土)16:00~18:00
講師:鈴木 和夫 先生(千葉大学大学院 薬学研究院)
演題:「セレンのメタボロミクス」
場所:化学研究所 新4Fセミナー室
連絡先:京都大学化学研究所 江崎 信芳 TEL:内線3240
 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちら■21COE講演会(No.66)が行われました。 【報告書】
日時:平成19年3月13日(火)16:00~18:00
講師:Prof. Dirk Michael Guldi (Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg)
演題:Carbon Nanostructures and Porphyrins - Exciting Opportunities for Solar Energy Conversion
場所:理学研究科6号館571号室
連絡先:京都大学理学研究科 化学専攻 大須賀 篤弘 TEL:内線4008
 ←ポスターはこちら
←ポスターはこちらこのページのTOPへ