|
||
|
||
化学専攻「卓越した大学院拠点形成」英語スキルアップコース(2013年夏期)
感想分子構造化学分科 博士後期課程1年 一条直規 記念撮影をした。5日間の成果を十分に発揮した発表会の後に。集合写真にはこの上ない笑顔が溢れていた。 正直なところ、あんなに楽しいセミナーになるとは思っていなかった。講師の先生は東大で教鞭を執る言語学の教授だそうだ。私は2週間後に海外での学会発表を控えていたので、英語でのプレゼンを指導してもらえる良い機会だと思い参加を決めた。 セミナー初日、ガリー先生が我々に最初に出した指示は、長机をどかすことだった。椅子を円形に並べるように、と。ガリー先生もその輪の中に加わる。このセミナーの成功の秘訣は、ガリー先生の熱意、先生と学生の距離感に加えて、先生が我々を信頼してくれたことにあると思う。 1日4時間のセミナーのほとんどは、学生同士で互いの英語を指摘し合う形式だった。これがかなり効果的だった。さすがに経験豊富な講師である。我々には切磋琢磨できるポテンシャルがあることを知っていたのだ。しかしそれだけでなく、我々は対話を重ねるにつれ、確実に親睦が深まっていった。空き時間の雑談の声も日に日に増えていった。 5日間のセミナーは、各々のスピーチで締め括られた。全員が100点満点の出来というわけにはいかないが、短期間とは思えぬ進歩を披露することができた。だが、写真の笑顔は達成感だけではないだろう。純粋に楽しかったからだと私は思う。我々は何も達成してはいない。これからも英語を磨き続けることを、互いに誓い合った。 理論化学分科 博士後期課程1年 内田芳裕 私は、英語で論文を書き、また口頭発表をするための、自分の英語の能力の現状と課題を知りたいと思い、今回の英語スキルアップセミナーに参加しました。これまで私は、英語で論文を書いたことがなく、せいぜい英語の要旨を書いたことがあるだけでした。そのため、自分の英語の能力にあまり自信を持っていませんでした。しかし、このセミナーを受講して、私は自身の英語能力を見直すことができたとともに、自信を持って英語を積極的に使うことの大切さを学びました。文の順序や接続詞の使い方などこれまで英語の文を書く際に感じていた疑問点を解決し、冠詞の用法や能動態と受動態の使い分けなどより良い文章を書くために英文を書く際に気を付けるべき点が分かりました。Gally先生にどのような文が一般的により読みやすく、どのような言い回しがよく使われているかについて、具体例を交えながら論理的に説明して頂いたおかげで、私も微妙なネイティブの感覚を少し得ることができたと思います。 また、私が今回このセミナーに参加して良かったと感じるもう一つの点は、化学専攻の他の研究室の大学院生と交流を持つことができ、どんな研究をしているかについて知ることができたことです。特に興味を持った分野については、セミナー後もお互いの研究について深く議論しました。セミナーでそれぞれの研究分野について英語で質問し、議論することで、自分も英語で討論できるという自信を持つこともできました。 最後に毎日の宿題はとても大変でしたが、その一方で一週間集中して英語の特訓に取り組んだことで、とても充実した一週間を過ごせたと思います。これからも積極的に英語を活用し、科学分野における国際的な交流を挑戦したいです。 表面化学分科 修士課程1年 施 安路 一週間の英語短期集中コースが無事に終わって良かったです。受講中の一週間は、本当に素晴らしい一週間でした。このコースの前に、英語で論文を書く、発表をするといったことは全くしたことがありませんでした。それらのことは実に難しいと思っていましたが、このコースが終わったとき、どんどん出来る感じがしました。 この5日間で、毎日自分が最初に書いた小論文を修正したり、peer viewといって、学生同士で論文を修正するといったことをしたりして過ごしました。実際、論文の書き方の他に色々なことを身につけました。 また、Gally先生がいつも優しくしてくださり、本当に感謝しています。このコースから色々 勉強しました。とてもありがたいと思います。 ナノスピントロニクス分科 修士課程1年 田中健勝 微妙なニュアンスの違いを日本語で訪ねたり教えてもらえる点が非常によかった。日本語も喋れる先生だと気軽に受講できるので今後も続けて欲しい。日本人が作る英文とネイティブの人が作る英文の違いを教えてもらえたのが良かった。冠詞に関する話はこれまで何度か聞いたことがあるけれどやはり難しかった。 分子分光学分科 修士課程2年 田中駿介 英語スキルアップセミナーでは大変お世話になりました。私としては有意義なセミナーでした。以下に箇条書きで有意義であった点、難しかった点を書きます。
今後もこのような機会があれば参加したい。 集合有機分子機能分科 修士課程2年 直田耕治 毎日の授業の初めには、英語のみを使って数人のグループ内でdiscussionを行いました。頭にすぐ解答は思い浮かぶものの、それをすぐに英語に直して口から発することはなかなか適いませんでした。当研究室にも海外PDが在籍し、英語をたまに話すことが有りますが、どうしても疎遠になりがちでした。この5日間では、そのような逃げ場所はなく、人と向かい合って、本当にゆっくりの英語でいいから何とか自分の意見を言えることはできたものの、まだまだ理想にはほど遠いと感じています。しかしながら、このような機会がなければ英語を話そうなどとは思わないので、ありがたかったです。
また、講義以外でも、普段交わらない別の研究室の方ともdiscussionでき、考えていること、意見を聞くことができ、互いに分からないところを教え合い、ちょっとした化学専攻の中での交流を深める機会にもなったのではないかと思います。 分子分光学分科 博士後期課程3年 宮田潔志 全体として非常に有意義に感じました。 10数人という割と少人数で一週間毎日交流をしていたため、研究室間の交流といった観点からも大変有意義でした。 特に難しくて困った点などはありませんでした。英語が苦手な人でも抵抗少なく取り組める、適切な課題設定をされていたと思います。 内容が良かっただけに、学生の参加人数が少ないのが非常にもったいないと思いました。 外部から講師を呼んでいる以上どうしても短期集中になり、例えば今回の場合は一週間まるまるこのコースに捧げることになるため、研究室の実験のスケジュールのやりくりなどが難しかった人もいたのだとは思いますが、研究室によってはこういった研究以外の活動に参加がしにくい雰囲気になってしまっているのかもしれません。 なにより、今回学んだことを今後に如何にして活かして行くかが大事だと思いますので、学んだことをどんどん実践していきたいと思います。 集合有機分子機能分科 博士後期課程1年 森 裕貴 本セミナーでは、ライティングやプレゼンテーションの指導だけでなく、英語を用いたディスカッションも行われました。 これにより、英語の能力のみならず、同時にコミュニケーション能力も鍛えることができたと思います。(副次的ではありますが、他研究室の学生と交流を持てたことも、個人的には非常に大きな収穫でした。 このように全く分野の異なる研究室の学生との交流も、また違った意味で重要だと思います。) 課題となった文章の作成に関しましては、実際に我々学生の書いた文章を目の前で改善していただき、細かい点から全体的な方針に至るまで、非常に丁寧に教えていただきました。 特に前置詞の使い方や関係代名詞の用法、そしてそれらを修正しながら文章の構成を再構築する方法等、基本的な点から実践的なテクニックまで、英語を書き慣れていない我々にとって、重要なポイントを学ぶことができたと思います。 他にも、日本語を非常に流暢にお話しになる講師のGally先生による「日本語的な英語」に対して、ネイティブの方が感じる違和感等のお話をして頂き、とても参考になりました。 ネイティブの先生に個別に教えていただく機会は学部時代からほとんどなく、本格的な指導を受けることは今回が初めてでしたが、セミナー全体を通して、「日本語的な英語」と「自然な英語」の違いを教えていただけたと感じています。 分子集合体分科 修士課程1年 山田一斗 僕がこのセミナーに参加しようと思った理由としては、自分の英語の能力がスピーキング、ヒヤリング、ライティングにおいて低かったからです。今回のセミナーのプログラムでは、ディスカッション、プレゼン、ライティングがメインであったため、自分の英語のスキルアップにかなり役立ちました。このセミナーでは学生同士で、ディスカッション、ライティングのチェックをし、改善していき、もし解決できない疑問があった場合は、ネイティブの先生に聞くというスタンスで行われました。これらのプログラムは授業形式ではなく、主体性を重要視して行われていたのが、さらに自分のスキルアップにつながったと思います。さらに参加者がM1~D3と幅広く、かつ分野の違う化学専攻の院生同士が集まり勉強することも今回のセミナーで魅力の1つだと思いました。普段なかなかできない他分野の院生の交流というだけでなく、研究・英語・その他ともに学ぶことで得られることもかなり大きかったです。全体を通して、以上の理由から今回セミナーに参加してとてもよかったと思いました。今後もこのような機会があれば、ぜひ参加したいと思います。 集合有機分子機能分科 博士後期課程2年 米田友貴
英語でのディスカッションは、やや難解でしたが、非常に良いスピーキングのトレーニングなりました。論理的に考えをまとめ、それを英語でうまく表現する、という過程は有意義であったと思います。英文添削の過程は、通常の添削とは異なり、仲間内で交換して見直しを繰り返す、という形式であり、これによって、文章を丁寧に見直す力が得られたと感じました。また、これにより自分の英文がどんどん良くなって行くことが分かり、モチベーションを得ることが出来ました。英語での口頭発表においては、普段は軽視しがちな、「論文と発表との違い」について、丁寧に説明をしていただき、どのように喋るか、ということについて新しい知見を得ることが出来ました。 Gally先生の解説も日本語、英語とも非常に分かりやすく、全体的にとても優れたセミナーであると感じました。 また、本来の目的とは外れますが、同じ化学棟に居ながらあまり交流の無い分野の異なる他研究室での研究内容に触れる良い機会ともなり、その点においても有意義でした。 |
||
| © Kyoto University 2008 |
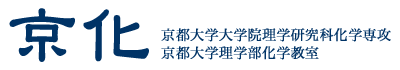
 夏季英語スキルアップコースを開催致しました。
夏季英語スキルアップコースを開催致しました。 授業の中盤から後半は自分の英語表現を先生や他の学生と一緒に、適切かどうか議論しました。勉強になったのは、特に冠詞の使い方、正しい論文の文章の流れについて、です。先生も学生側からの質問に的確に答えて下さり、時にはジョークを交えて笑い合い、非常に有意義かつ楽しいものでした。
授業の中盤から後半は自分の英語表現を先生や他の学生と一緒に、適切かどうか議論しました。勉強になったのは、特に冠詞の使い方、正しい論文の文章の流れについて、です。先生も学生側からの質問に的確に答えて下さり、時にはジョークを交えて笑い合い、非常に有意義かつ楽しいものでした。 英語スキルアップセミナーは、毎日適当な議題について英語でのディスカッションを行い、その後、予め準備した研究内容の要約をお互いに添削し(peer review)論文様の体裁にまとめ、また、2日目以降からは英語での口頭発表の原稿の作成およびその添削も行い、最終日の午後より英語で実際に発表、という流れで行われました。
英語スキルアップセミナーは、毎日適当な議題について英語でのディスカッションを行い、その後、予め準備した研究内容の要約をお互いに添削し(peer review)論文様の体裁にまとめ、また、2日目以降からは英語での口頭発表の原稿の作成およびその添削も行い、最終日の午後より英語で実際に発表、という流れで行われました。